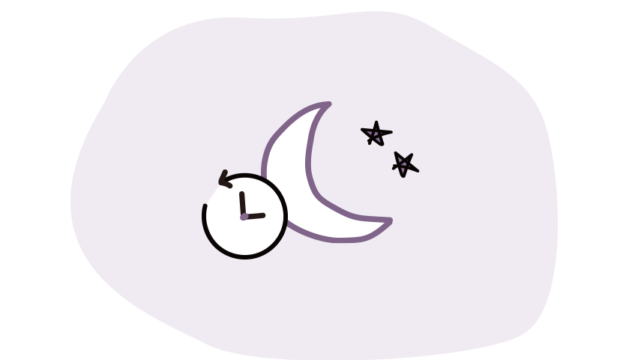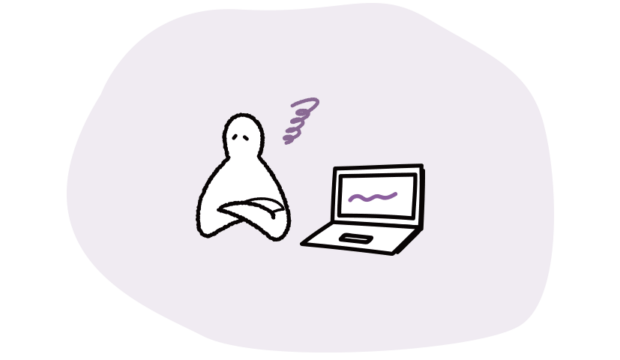発達障害を持つ人々は、一般的に睡眠に関する問題を抱えやすいとされています。特に自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)を持つ方々においては、睡眠の質や睡眠時間に関する悩みが頻繁に見られます。今回は、発達障害による睡眠の悩みとその解消方法について詳しく解説します。
1. 発達障害と睡眠の関係
発達障害に関連する睡眠の問題は、さまざまな要因から生じることがあります。発達障害の特性として、感覚過敏、情緒の不安定、集中力の欠如などが挙げられますが、これらの要素が睡眠に直接的な影響を与えることがあります。具体的には以下のような悩みが発生することが多いです。
〇 入眠困難:集中力やリラックスすることが難しく、寝つくのに時間がかかる。
〇 夜間覚醒:夜中に目を覚まし、再び眠ることができない。
〇 過剰な寝坊:朝早く起きるのが難しく、昼夜逆転の生活が続くことがある。
〇 感覚過敏:騒音や光、温度などの環境要因が睡眠を妨げる。
2. 睡眠の悩みを引き起こす原因
発達障害による睡眠障害の背景には、以下のようなさまざまな原因が考えられます。
2.1 感覚処理の困難
自閉症スペクトラム障害(ASD)を持つ人々は、感覚過敏があることが多いです。これにより、夜間の騒音や部屋の明るさ、寝具の素材などが気になり、リラックスできないことがあります。
2.2 不安やストレス
ADHDの特徴として、感情の調整が難しいことがあります。このため、睡眠前に不安や興奮が強くなり、入眠を妨げる原因となることがあります。また、日中に集中できなかったことへのストレスが夜に出ることもあります。
2.3 体内時計の乱れ
発達障害を持つ方々は、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れが起こりやすいです。これが原因で、昼と夜のリズムが逆転してしまい、睡眠障害を引き起こします。
2.4 過度のエネルギー消費
ADHDの方々は、活動量が多いことがあり、エネルギーを消費しすぎて寝る時間になってもリラックスできず、眠りにつくのが難しくなることがあります。
3. 発達障害による睡眠の悩みの解消方法
発達障害に伴う睡眠の悩みを解消するためには、適切な対処法が必要です。ここでは、睡眠の質を向上させるための実践的な方法をいくつか紹介します。
3.1 規則正しい生活リズムを作る
発達障害による睡眠障害は、体内時計の乱れが原因の一つです。そのため、毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝ることを心掛けることが重要です。寝る時間を決め、徐々に規則正しい生活を身につけることで、体内時計を整えることができます。
![]()
3.2 寝室の環境を整える
睡眠の質を向上させるためには、寝室の環境を整えることが大切です。静かな場所を選び、騒音を減らす工夫をしましょう。暗い部屋を作り、寝具やパジャマが快適であることも重要です。温度や湿度も調整して、快適な睡眠環境を作りましょう。
3.3 就寝前のリラックス法
就寝前にリラックスすることが、より深い眠りを促進します。例えば、温かいお風呂に入る、瞑想や深呼吸を行う、リラックスできる音楽を聴くなどの方法が効果的です。特に、スクリーン(スマホやPCなど)の使用を寝る1時間前に避けることが、睡眠の質を改善するために有効です。
![]()
3.4 睡眠障害に対応するサポートを受ける
発達障害による睡眠障害が長期にわたって続く場合、専門的なサポートを受けることが必要です。心療内科や睡眠外来の医師によるカウンセリングや薬物療法が、睡眠改善に役立つことがあります。
![]()
3.5 運動と食事の改善
日中に軽い運動を行うことも、夜の眠りを助けます。適度な運動は、体をリラックスさせ、眠りにつきやすくするために効果的です。また、寝る前の食事にも気をつけましょう。カフェインや過度の食事を避けることで、睡眠を妨げる原因を減らすことができます。
![]()
4. まとめ
発達障害による睡眠の悩みは、個人差が大きく、原因も多岐にわたります。しかし、生活リズムの整備や環境の調整、リラックス法を取り入れることで、睡眠の質を改善することが可能です。もし、睡眠障害が深刻な問題となっている場合は、専門的なサポートを受けることも考慮しましょう。自分に合った方法を見つけ、質の高い睡眠を確保することが、心身の健康を保つために非常に重要です。
あわせて読みたい
>【医師監修】大人のADHDとは?気づきにくい症状と日常での困りごと
>【医師監修】ADHD・ASDの特性から起こりやすい日常の困りごと

2025.04.09
【医師監修】ADHD・ASDの特性から起こりやすい日常の困りごと
ADHD(注意欠陥・多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム障害)は、発達障害の一形態として知られ、個人の認知機能や社会性、行動に特性を持つ状態です。これらの特性が日常生活に影響を及ぼすことがあり、特に仕事や家庭生活、対人関係において多くの困りごとが生じやすいです。本コラムでは、ADHD・ASDそれ...