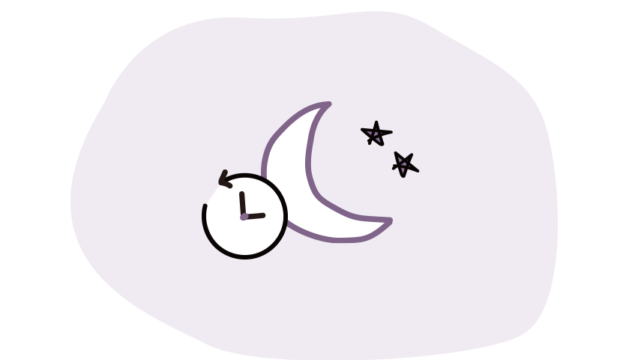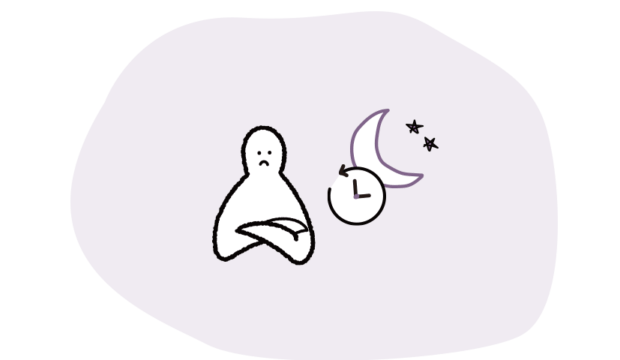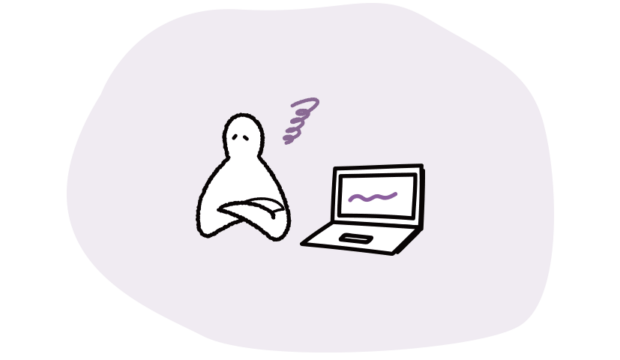ADHD(注意欠陥・多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム障害)は、発達障害の一形態として知られ、個人の認知機能や社会性、行動に特性を持つ状態です。これらの特性が日常生活に影響を及ぼすことがあり、特に仕事や家庭生活、対人関係において多くの困りごとが生じやすいです。本コラムでは、ADHD・ASDそれぞれの特性が引き起こす困りごとと、それに対する対処法を解説します。
1. ADHDの特性と困りごと
ADHDは、主に「注意の欠如」「多動」「衝動性」の3つの特徴を持ちます。これらの特徴が個人の生活においてどのように困りごとを引き起こすのかを具体的に見ていきましょう。
1-1. 注意の欠如による困りごと
ADHDの特徴の一つは、注意が散漫になりやすいことです。これにより、次のような困りごとが生じることがあります。
〇 仕事や学業でのミスが増える:
細かい作業や注意を要する作業をこなす際に、集中力が続かずミスが増えてしまいます。特に、長時間同じ作業を続けることが難しく、作業の完了が遅れることもあります。
〇 日常生活での忘れ物や遅刻:
予定を忘れやすく、物事を後回しにしてしまうことが多いです。重要な電話や約束をすっぽかしてしまうことがあるため、対人関係で信頼を損ねることにもつながります。
1-2. 多動による困りごと
多動性が強いADHDの人は、静かにしていることが難しく、次のような困りごとが発生しやすいです。
〇 会議や集まりで落ち着けない:
じっとしていることができず、体を動かしてしまうため、会議や授業で注意を引きすぎてしまうことがあります。静かな環境が求められる場面では、周囲に迷惑をかけることもあります。
〇 衝動的な行動や発言:
思いついたことをすぐに口に出してしまったり、場の雰囲気を無視して行動することがあります。このため、対人関係においてトラブルが起きやすいです。
1-3. 衝動性による困りごと
衝動的な行動がADHDの特徴の一つです。これにより次のような問題が生じることがあります。
〇 衝動的な買い物や借金:
衝動的に物を買ってしまったり、安易にお金を借りてしまうことがあります。これは経済的な困難を引き起こす原因となります。
〇 感情のコントロールが難しい:
ストレスやイライラがたまりやすく、瞬間的な感情に任せて行動することが多いです。人間関係で衝突が起こることもあります。
2. ASDの特性と困りごと
ASDは、社会的なコミュニケーションや対人関係における特性、また反復的な行動パターンが特徴です。ASDの特性から生じる困りごとは、主に次のようなものです。
2-1. 社会的コミュニケーションの困難
ASDの人は、社会的なサインを読み取るのが難しいことがあり、コミュニケーションで困りごとが生じやすいです。
Tips〇 非言語的なサインの誤解:
相手の表情や身振り、言葉の裏にある感情や意図を読み取るのが難しいことがあります。そのため、相手の気持ちを理解しきれず、誤解が生じることがあります。
〇 会話の順序がうまく取れない:
会話が一方通行になりがちで、相手の話を途中で遮ったり、自分が話したいことを優先しすぎてしまうことがあります。このため、会話が成立せず、関係性がギクシャクすることがあります。
2-2. 狭い興味に偏りがち
ASDの人は特定の興味や趣味に強くこだわる傾向があり、次のような困りごとを引き起こすことがあります。
Tips〇 仕事や学業において他の興味が優先される:
特定の興味に没頭しすぎて、他の仕事や学業が後回しになり、成果が上がらないことがあります。このため、職場や学校での評価が低くなることがあります。
〇 日常生活での柔軟性の欠如:
予定変更や突然の出来事に対応するのが苦手で、慣れた環境やルーチンが乱れると強いストレスを感じることがあります。
2-3. 感覚過敏や感覚鈍麻
ASDの人は感覚に過敏であったり、逆に鈍感であることがあります。このため、次のような困りごとが生じやすいです。
Tips〇 音や光に敏感:騒音や強い光、特定の匂いなどに過敏に反応することがあり、公共の場や仕事場での過剰な刺激が大きなストレスとなります。
〇 身体的な感覚に鈍感:痛みに鈍感であったり、逆に小さな不快感にも過敏に反応することがあり、自己管理や健康維持が困難になることがあります。
3. ADHD・ASDの特性を理解し、対処するために
ADHDやASDの特性が引き起こす困りごとは、理解と工夫を通じて改善できる場合があります。以下は、特性を理解し、日常生活をサポートするための方法です。
〇 環境の整備
〇 コミュニケーションの工夫
〇 専門的なサポート
4. まとめ
ADHDやASDの特性が引き起こす困りごとは、個人の生活にさまざまな影響を与えます。しかし、特性を理解し、適切な対処法を講じることで、困難を乗り越えることが可能です。身近な人や専門家と協力し、支援を受けることで、生活の質を向上させることができます。
あわせて読みたい
>【医師監修】大人のADHDとは?気づきにくい症状と日常での困りごと
>【医師監修】心の不調、心療内科受診のサインはどう見極めるべき?
>【医師監修】カサンドラ症候群とは?症状、治療法、そして家族やパートナーとの向き合い方

2025.02.17
【医師監修】大人のADHDとは?気づきにくい症状と日常での困りごと
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもだけの問題と思われがちですが、大人になっても症状が続く場合があります。実際、大人のADHDは、仕事や日常生活において様々な困りごとを引き起こすことがあり、その影響は本人だけでなく、周囲の人々にも及びます。本記事では、大人のADHDの特徴や日常生活での課題について...