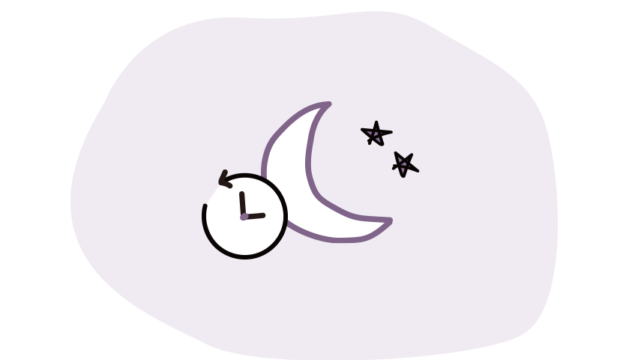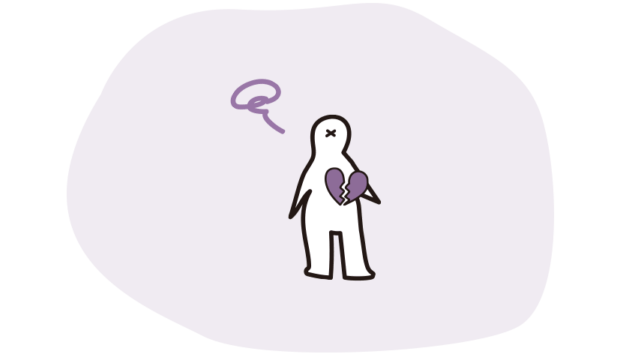秋になると、「なんとなく気分が沈む」「朝起きるのがつらい」「疲れが取れにくい」と感じる方が増えます。
季節の変わり目で体がだるいだけと思って放置してしまう方も多いですが、その不調、実は秋うつが関係しているかもしれません。
本記事では、秋に起こりやすい心と体の変化、そして「ただの疲れ」と「秋うつ」の違いを医師がわかりやすく解説します。
秋に不調を感じやすい理由
秋は、夏の疲れが残る中で急に気温や日照時間が変化し、体にも心にも負担がかかりやすい季節です。特に次のような要因が、自律神経やホルモンバランスに影響を与えます。
1. 日照時間の減少
秋が深まるにつれて日が短くなり、セロトニン(心の安定に関わる脳内物質)の分泌が減少します。セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや不安感が強くなりやすくなります。
2. 気温差と自律神経の乱れ
朝晩の冷え込みや日中との寒暖差が大きくなると、体温を調整する自律神経が過剰に働き、疲労感やだるさ、集中力の低下を招きます。
3. 夏の疲れの蓄積
猛暑や睡眠不足など、夏のダメージが体内に残っていると、秋に入ってからその反動で強い疲れや不調を感じるケースもあります。
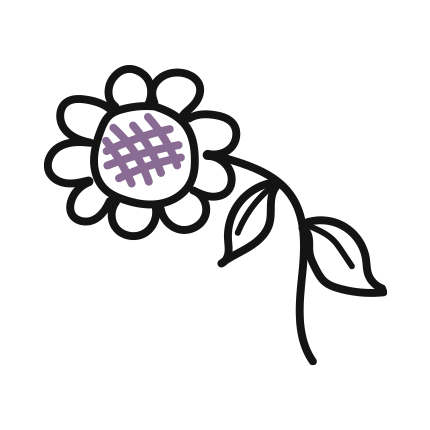
「秋うつ」と「ただの疲れ」はどう違うのか?
普通の疲れ
- 睡眠や休養を取ると回復する
- 一時的なだるさや眠気が中心
- 気分の浮き沈みはあっても長引かない
秋うつ(季節性うつ)
- 2週間以上、気分の落ち込みや意欲低下が続く
- 眠っても疲れが取れない
- 食欲が増す(特に甘いものや炭水化物を欲する)
- 仕事や家事への興味が薄れる
- 朝が特につらい、起き上がれない
秋うつの特徴は、「体の疲れ」だけでなく「心のエネルギーが低下する」ことです。また、一般的なうつ病と比べて冬に近づくほど悪化しやすいという季節的な特徴があります。
秋うつになりやすい人の傾向
- 真面目で責任感が強い
- 睡眠リズムが不規則になりがち
- 在宅勤務などで外出・日光を浴びる時間が少ない
- ストレスを感じやすく、気持ちをため込みやすい
- 過去にうつ病や自律神経失調症の経験がある
これらの傾向がある方は、季節の変化に伴う心身の影響を受けやすいため、早めのセルフケアや生活習慣の見直しが大切です。
秋うつを防ぐための生活習慣のポイント
1. 日光を意識的に浴びる
朝の時間帯に日光を浴びることで、体内時計が整い、セロトニンの分泌が促されます。短い時間でも、朝の散歩や通勤時に陽を感じる習慣を意識してみましょう。
2. 規則正しい睡眠リズムを保つ
寝る時間と起きる時間を一定にすることで、自律神経のバランスを整えられます。夜更かしやスマートフォンの見過ぎにも注意が必要です。
3. 栄養バランスを意識する
秋は甘いものを欲しやすい時期ですが、ビタミンB群やタンパク質、オメガ3脂肪酸など脳の働きを助ける栄養素を意識して取り入れましょう。
4. 適度な運動を取り入れる
軽いウォーキングやストレッチ、ヨガなどは血流を良くし、ストレス解消にも効果的です。運動によりセロトニンが増え、気分が安定しやすくなります。
医療機関に相談する目安
次のような状態が2週間以上続く場合は、医療機関への相談を検討しましょう。
- 朝起きるのが極端につらい
- 何をしても気分が晴れない
- 食欲・体重の変化がある
- 仕事や家事に集中できない
- 無気力・涙もろさが続く
「秋の疲れ」だと思っていた不調が、実は季節性うつ(秋うつ)だったという方も少なくありません。早めの受診は回復を早める大切な一歩です。
まとめ
秋は気温や日照時間の変化により、心も体もバランスを崩しやすい季節です。
「なんとなくだるい」「気分が落ち込む」と感じたら、無理をせず立ち止まり、まずは自分の心と体の声に耳を傾けてみてください。
必要に応じて医療機関に相談することで、適切なケアを受けながら、秋を穏やかに過ごすことができます。
心の不調を早めに見つけ、整えていくことが、明日をより軽やかに生きる第一歩です。
あわせて読みたい
>【医師監修】季節性うつとは?症状、原因、治療法、対処法を解説
>【医師監修】眠れないのは自律神経の乱れが原因?不眠と自律神経失調症の関係
>【医師監修】天気予報とメンタルヘルス:パニック障害患者が気をつけるべきポイント

2025.03.19
【医師監修】季節性うつとは?症状、原因、治療法、対処法を解説
季節性うつ(季節性情動障害、Seasonal Affective Disorder:SAD)は、特定の季節に発症しやすいうつ病の一種です。特に秋から冬にかけて日照時間が短くなる時期に、症状が悪化することが多く見られます。この記事では、季節性うつの症状や原因、治療法、そしてその対処法についてご紹介しま...