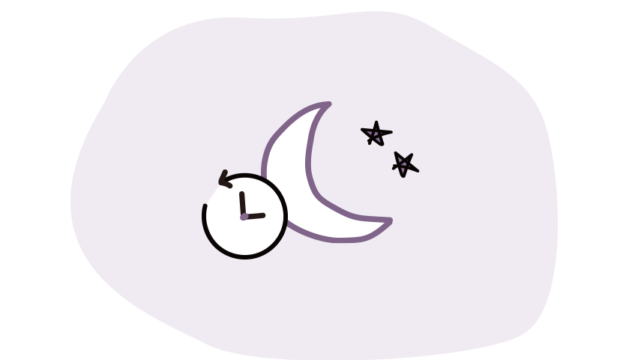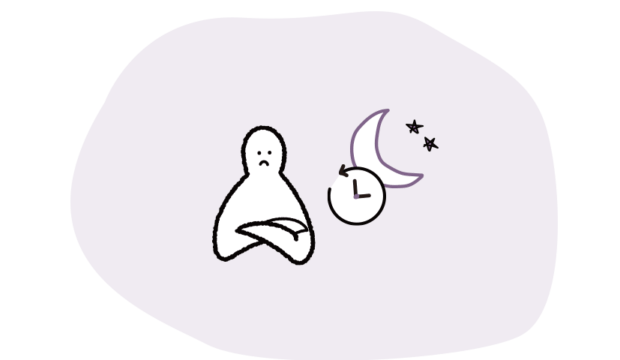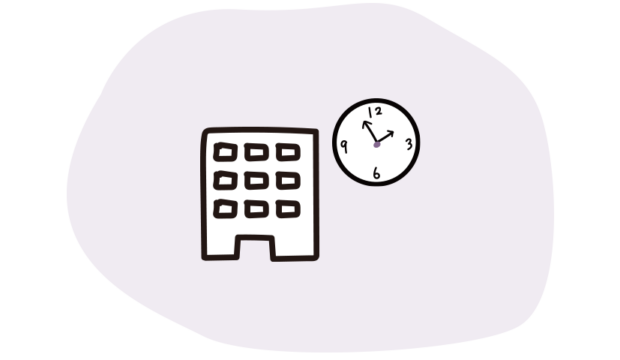「夜になってもなかなか眠れない」「眠っても疲れが取れない」──そんな不眠の悩みを抱えていませんか?
特に、システムエンジニア(SE)として日々長時間PC作業を行っている方の中には、慢性的な不眠に悩まされている方も少なくありません。
本記事では、長時間のPC作業が不眠を引き起こすメカニズムや、SEに特有の生活習慣による影響について解説します。最後に医師によるセルフケアのポイントや受診の目安についても紹介しておりますので、ご参考になればと思います。
1. 長時間PC作業と不眠の関係
PC作業は現代社会において不可欠な業務の一部ですが、目や脳への刺激が強く、就寝前まで続けると睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
特に、夜遅くまで画面を見続けることで、脳が興奮状態となり、寝つきが悪くなる・途中で目が覚める・早朝に目覚めるといった不眠の症状が現れることがあります。
また、PC画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、体内時計(サーカディアンリズム)を乱すこともわかっています。
2. SEに多いライフスタイルの特徴
システムエンジニアの方は、以下のような生活習慣や勤務形態により、不眠を引き起こしやすい傾向があります。
- プロジェクトによって勤務時間が不規則になる
- 深夜までの業務や納期直前の長時間労働が続く
- 緊張やプレッシャーが高く、就寝後も考えごとが止まらない
- 日中の運動量が少なく、身体的な疲労が足りない
- 昼夜逆転の生活リズムになりがち
これらの習慣が続くことで、睡眠の質が下がり、慢性的な疲労感や注意力の低下、集中力の欠如につながることがあります。
3. ブルーライトと体内時計の乱れ
PCやスマートフォン、タブレットなどの画面から発せられるブルーライトは、日中の自然光と似た波長を持ち、脳に「今は昼間だ」と誤認させてしまう作用があります。
これにより、夜になっても脳が覚醒状態を維持し、寝つきが悪くなる・夜中に目が覚める・眠りが浅くなるといった不眠症状が現れるのです。
特に就寝1〜2時間前までPCを見ている習慣がある方は、意識的にブルーライトの暴露を減らす工夫が必要です。
4. ストレスと自律神経の関係
SEの仕事は技術的な高度さだけでなく、納期や障害対応など精神的なストレスも大きい職種です。
強いストレスが続くと、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経には、日中活動する際に優位になる「交感神経」と、休息や睡眠時に働く「副交感神経」があります。
ストレスが続くと交感神経が過剰に働いた状態が続き、夜になってもリラックスできず、眠れない原因になります。医師によると、不眠の背景には「自律神経の乱れ」があるケースも多く、単なる生活習慣の問題だけではないこともあるそうです。
5. 不眠が招く心身の不調
睡眠は、脳や身体を回復させる大切な時間です。
それがうまくとれない状態が続くと、次のような不調が現れる可能性があります。
- 慢性的な疲労感・倦怠感
- 集中力や記憶力の低下
- 頭痛や肩こり
- イライラや抑うつ気分
- 胃腸の不調
- 自律神経失調症のような症状(めまい・息苦しさなど)
このような不調がある場合、「たかが睡眠不足」と軽視せず、根本的な原因を探ることが大切です。
6. 不眠へのセルフケアと予防法
医療機関では、以下のようなセルフケアが推奨されています。
- 就寝前のデジタルデトックス
寝る1〜2時間前からPCやスマホの使用を控え、間接照明でリラックスする習慣を作りましょう。 - 就寝・起床の時間を一定に保つ
休日も含めて毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計を整えやすくなります。 - カフェイン・アルコールを控える
特に夕方以降のコーヒーやアルコールは、睡眠の質を低下させることがあります。 - 軽い運動習慣を取り入れる
日中の軽い運動は、自律神経を整える効果があり、睡眠の質向上に役立ちます。 - ストレスをためこまない
定期的に心をリセットする時間を設けたり、相談できる相手を持つことも大切です。
7. 症状が続くときは医療機関へ
数日〜1週間の不眠であれば、一時的なストレスや環境変化によるものかもしれません。
しかし、2週間以上眠れない状態が続いたり、日常生活に支障をきたすほどの不調がある場合は、医療機関に相談することをおすすめします。
不眠は、うつ病や不安障害、ホルモンバランスの乱れなどの一症状として現れることもあるため、専門的な評価が必要となることがあります。
8. まとめ
長時間のPC作業が続くSEの方にとって、不眠は決して珍しい悩みではありません。
しかし、それを放置してしまうと、心身の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、医師による知見をもとに、PC作業と不眠の関係性、自律神経の乱れ、セルフケアの方法について解説しました。
ご自身の不調が生活習慣によるものなのか、あるいは医療的なサポートが必要なのか、早めに気づくことが重要です。
「眠れないこと」に悩んだら、どうかひとりで抱え込まず、医療機関にご相談ください。
あわせて読みたい
>【医師監修】SEのうつ病リスクを減らすために知っておきたいこと
>【医師監修】メンタル不調で休職する前に知っておきたい10のこと
>【医師監修】不眠症と自律神経失調症の違いは?見極めポイントと対処のヒント

2025.08.29
【医師監修】不眠症と自律神経失調症の違いは?見極めポイントと対処のヒント
本記事では、不眠症と自律神経失調症という、どちらも日常生活に大きな影響を与える症状の違いを医師が解説します。どちらの症状も「眠れない」「体調がすぐれない」など似たような悩みとして感じやすいですが、原因や対処法は異なります。正しく理解し、適切な対応ができるようになることが大切です。 1. 不眠症と...