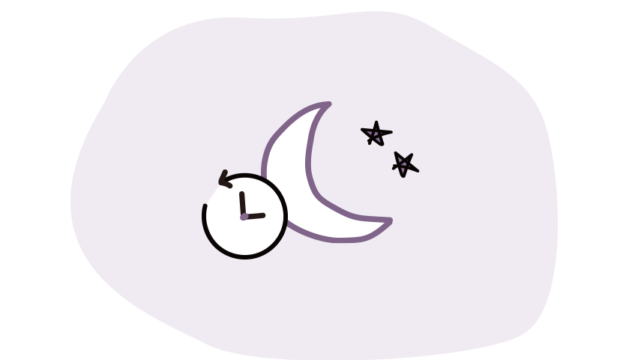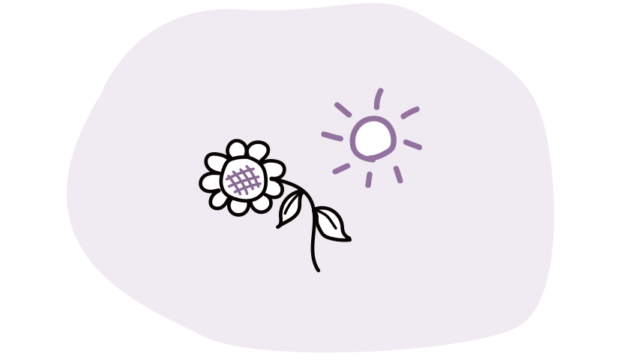6月病とは?
6月病とは、6月に入ってから感じる心身の不調を指す言葉であり、正式な医学用語ではありません。新年度が始まり2~3か月が経過し、新しい環境に適応しようと頑張ってきた人が、心身の疲れを感じやすくなる時期に現れる症状です。特に、仕事や学校に慣れ始めたころに緊張の糸が緩み、無気力やストレスが表面化することが原因とされています。
5月病との違い
5月病は、新生活や新しい環境に適応できずにストレスが蓄積し、ゴールデンウィーク明けごろに心身の不調が出る症状です。一方で、6月病は環境に適応できたにもかかわらず、疲れやストレスが蓄積して体調を崩すという点が異なります。また、5月病は「適応障害」の一種とされることが多いですが、6月病は慢性的なストレスが引き金となることが多く、うつ症状へと移行するリスクもあります。
6月病の主な症状
6月病の症状は個人差がありますが、主に以下のようなものが見られます。
精神的な症状〇 無気力、やる気が出ない
〇 不安や焦りを感じる
〇 気分が落ち込みやすい
〇 集中力の低下
〇 イライラしやすい
身体的な症状〇 慢性的な疲労感
〇 頭痛や肩こり
〇 胃腸の不調(食欲不振、胃の痛みなど)
〇 不眠、または過眠
6月病になりやすい人の特徴
以下のような特徴を持つ人は、6月病になりやすいといわれています。
〇 真面目で責任感が強い
〇 新しい環境に適応しようと頑張りすぎる
〇 完璧主義である
〇 ストレスを発散する方法が少ない
〇 季節の変化に敏感
6月病の予防と対策
6月病を防ぐためには、日常生活でのストレス管理が重要です。
1. 生活リズムを整える
![]()
-
- 規則正しい食事と睡眠を心がける
- 毎日同じ時間に寝起きする
- 朝に日光を浴びて体内時計を調整する
2. 適度な運動を取り入れる
![]()
-
- 軽いストレッチや散歩を習慣にする
- ヨガや深呼吸でリラックスする
- 週に数回、汗をかく程度の運動をする
3. ストレス発散を意識する
![]()
-
- 趣味の時間を大切にする
- 友人や家族と会話する
- カフェや自然の中でリフレッシュする
4. 仕事や勉強の負担を調整する
![]()
-
- 無理をせず、適度に休憩をとる
- 完璧を求めすぎない
- 仕事のスケジュールを見直し、負担を軽減する
6月病が悪化すると?
6月病の症状が長引いたり、強くなったりすると、うつ病へと進行する可能性があります。「何をしても楽しくない」「毎日が憂うつ」「食欲が極端に落ちる/増える」などの症状が2週間以上続く場合は、早めに医療機関に相談することをおすすめします。
まとめ
6月病は、新生活に適応した後に心身の疲れが出てくることで起こるストレス反応です。5月病とは異なり、環境に慣れた後に発症するのが特徴であり、放置すると慢性的なうつ状態に進行することもあります。規則正しい生活習慣を意識し、適度なストレス発散を行うことで、6月病を防ぐことができます。もし症状が長引くようであれば、心療内科や精神科でサポートを受けることを検討しましょう。
あわせて読みたい
>【医師監修】梅雨の季節に要注意!気圧の変化とうつ症状の関係
>【医師監修】心の不調、心療内科受診のサインはどう見極めるべき?
>【医師監修】新生活で感じる心の不調とは?原因と対処法を解説
>【医師監修】「雨の日はやる気が出ない…」雨とうつの関係性
>【医師監修】眠れない夜が増えたら要注意!更年期に多い睡眠トラブルとは

2025.05.21
【医師監修】梅雨の季節に要注意!気圧の変化とうつ症状の関係
梅雨時期に気分が落ち込むのはなぜ? 梅雨の季節になると、なんとなく気分が落ち込んだり、やる気が出なかったりすることはありませんか? これは単なる「気のせい」ではなく、実際に気圧の変化が私たちの体と心に影響を与えている可能性があります。 気圧の変化がもたらす体と心への影響 気圧が下がると、私たちの体は...