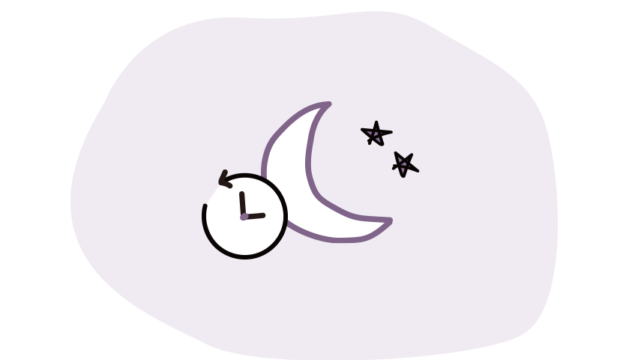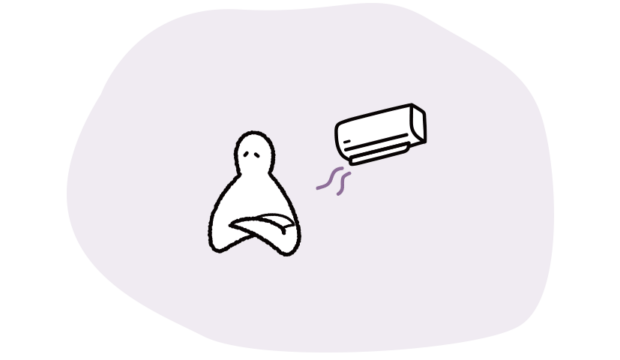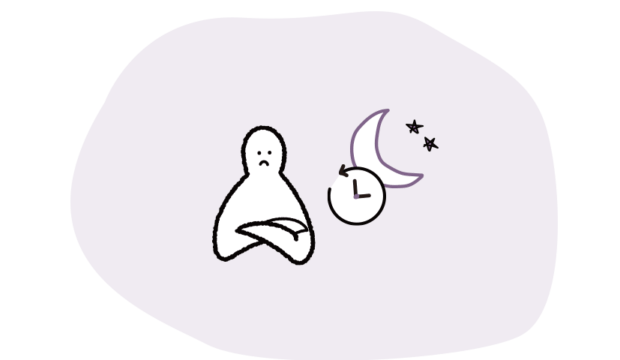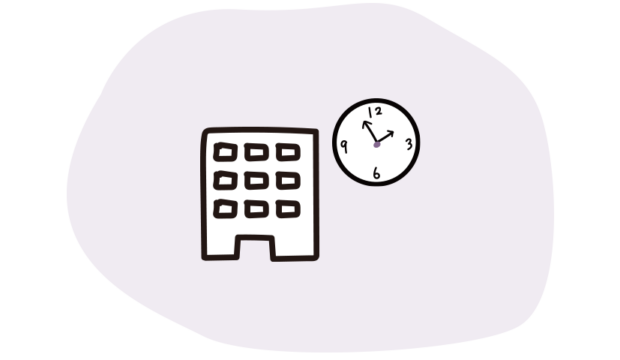「最近、夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠ったはずなのに疲れが取れない」――そんなお悩みを抱えていませんか?それは、働きすぎによる“隠れ不眠”かもしれません。
特に管理職の立場にある方は、責任やストレスが多く、睡眠の悩みを自覚しづらい傾向があります。「まだまだ頑張らないと」と、自分の健康を後回しにしてしまうことも少なくありません。
本記事では、医師による解説のもと、働きすぎの管理職に多く見られる“隠れ不眠”の実態と、その背景、対処法についてわかりやすくご紹介します。ご自身や身近な方の睡眠の質を見直すきっかけとして、ぜひご一読ください。
働きすぎる管理職に多い“隠れ不眠”とは?
“隠れ不眠”とは、本人が「眠れている」と感じていても、実際には睡眠の質が低下しており、心身に影響が出ている状態を指します。医学的には「不眠症」とまでは診断されなくても、健康上のリスクを伴うことがあるため、注意が必要です。
![]()
特に管理職の方は以下のような特徴から、隠れ不眠になりやすい傾向があります。
- 仕事のプレッシャーが大きく、心が常に緊張状態にある
- 早朝出勤・深夜の対応などで生活リズムが不規則
- 部下や家族の前では疲れや不調を見せにくい
- 睡眠時間が短くても「問題ない」と思い込みやすい
これらの状態が続くと、知らず知らずのうちに慢性的な睡眠不足や睡眠の質の低下を招き、日中のパフォーマンス低下、疲労の蓄積、さらには生活習慣病のリスクにもつながってしまいます。
隠れ不眠のサインを見逃さないで
以下のような症状に心当たりがある場合、隠れ不眠の可能性があります。
- 朝、起きてもスッキリしない
- 寝つきが悪い、または夜中に何度も目が覚める
- 夢ばかり見て熟睡感がない
- 午後になると強い眠気がくる
- 休日に長時間寝てしまう
- イライラしやすく、集中力が続かない
- 肩こりや頭痛、胃の不快感が慢性的にある
これらは身体が「きちんと休めていない」サインです。不眠というと「一睡もできない」というイメージを持つ方が多いのですが、隠れ不眠の場合、「眠れている気がする」けれど「疲れが取れない」ことが特徴です。
なぜ管理職に“隠れ不眠”が多いのか?
1. 責任の重さとプレッシャー
組織をまとめる立場にある管理職は、日々の意思決定や部下のマネジメントに加え、上司や取引先との調整など、多くのプレッシャーを受けやすい環境にあります。この心理的なストレスが脳を覚醒させ、就寝時にもリラックスできない状態が続きます。
2. ワークライフバランスの乱れ
「部下が帰ってからが自分の仕事」といったように、長時間労働が常態化しやすい管理職。帰宅後もスマートフォンやパソコンで業務連絡が入り、寝る直前まで仕事モードが抜けない方も多いのではないでしょうか。
3. 年齢による睡眠の変化
30代後半〜60代の方は、加齢によって睡眠が浅くなったり、途中で目が覚めやすくなったりする傾向があります。こうした加齢による睡眠の変化に、仕事のストレスが重なると、“隠れ不眠”がより深刻になるケースも見られます。
“隠れ不眠”がもたらすリスクとは?
睡眠の質が低下すると、心身にさまざまな悪影響が及びます。医師によると、以下のようなリスクが指摘されています。
生活習慣病のリスク増加
睡眠不足は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こす要因となります。また、免疫力の低下も招くため、感染症にもかかりやすくなります。
メンタルヘルスへの影響
不眠状態が続くと、うつ病や不安障害のリスクも高まります。特に責任ある立場にある方ほど「自分が頑張らないと」と無理をしがちですが、それが心の限界を見逃す原因にもなります。
判断力・集中力の低下
十分な睡眠がとれていないと、判断ミスや集中力の低下につながり、業務上のトラブルを引き起こす可能性も。ミスをしてしまった自分を責めることで、さらにストレスが強まり、不眠が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
睡眠の質を改善するためのセルフケア
“隠れ不眠”を改善するには、生活習慣を見直すことが第一歩です。以下のようなセルフケアを試してみましょう。
睡眠前のルーティンを整える
毎晩同じ時間に入浴し、照明を暗くしてリラックスする時間をつくることで、自然と眠りやすくなります。寝る直前までスマホやパソコンを見る習慣は、睡眠の質を下げる原因になります。
就寝前の思考を手放す
「明日の会議がうまくいくか心配」「メールの返信を忘れていないか」など、考えが止まらないときは、ノートに書き出すなどして、頭の中を“空”にする習慣も有効です。
カフェイン・アルコールの摂取に注意
夕方以降のコーヒーやお酒は、眠りを浅くしてしまう原因になることがあります。特にアルコールは一時的に眠気を感じさせますが、夜中に覚醒しやすくなるため注意が必要です。
病院を受診する目安とは?
セルフケアを行っても不眠の状態が2週間以上続く、日中の生活に支障が出ていると感じる場合は、医療機関に相談することをおすすめします。
「眠れない」という訴えだけでなく、「疲れが取れない」「いつも体がだるい」といった症状も、医師にとって重要な手がかりとなります。
また、不眠の背後に身体的な病気(睡眠時無呼吸症候群、うつ病、甲状腺疾患など)が隠れていることもあるため、自己判断せず、医療機関での早めの対応が大切です。
まとめ
管理職という立場上、周囲に弱音を吐けず、「眠れないくらいで」とがまんしてしまいがちな方も多いかもしれません。しかし、睡眠は健康の土台です。見えない不調を放っておくことが、将来的な病気やパフォーマンス低下につながる可能性もあります。
本記事でご紹介したように、“隠れ不眠”には日々の生活の見直しと、必要に応じた医療機関での相談が効果的です。
「もしかして自分も」と思ったときこそ、立ち止まって心と体の声に耳を傾けてみてください。睡眠の質を見直すことは、自分自身だけでなく、チームや家族を守る第一歩でもあります。
あわせて読みたい
>【医師監修】眠れないのは自律神経の乱れが原因?不眠と自律神経失調症の関係
>【医師監修】不眠症と自律神経失調症の違いは?見極めポイントと対処のヒント
>【医師監修】その不眠、マネジメントストレスが原因かも?管理職に多い睡眠トラブルとは
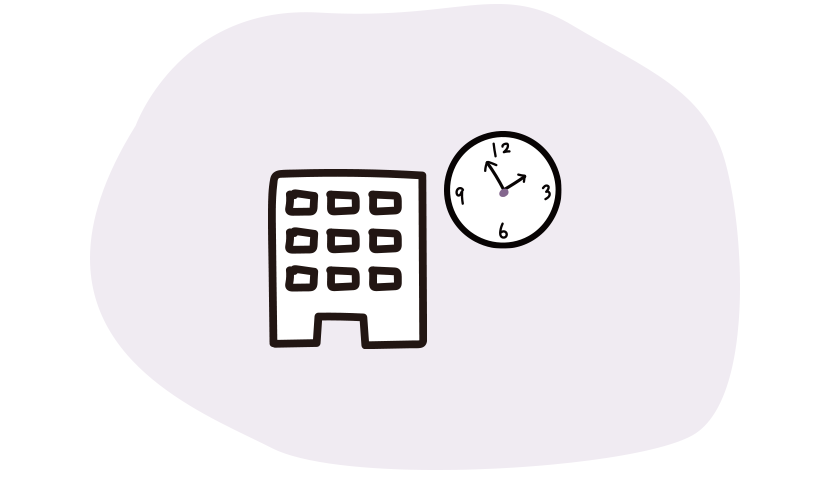
2025.10.20
【医師監修】その不眠、マネジメントストレスが原因かも?管理職に多い睡眠トラブルとは
最近、夜なかなか眠れない。眠っても途中で目が覚めてしまう――。こうした不眠の悩みを抱える方は少なくありません。特に、仕事で責任ある立場にある管理職の方の中には、慢性的な睡眠の質の低下に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。 ストレスが原因かもしれないと感じつつも、「自分が弱いだけかもしれない」「病院...