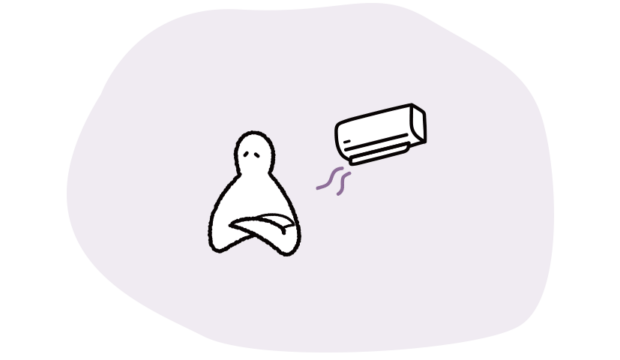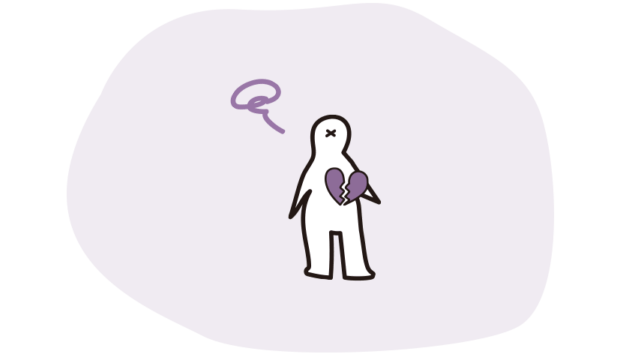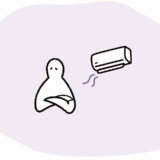育児は、子どもの成長を間近で見守れる尊い時間である一方で、親自身の心身に大きな負担がかかる時期でもあります。
「子どもに怒ってしまった」「思うようにできない自分が嫌だ」「他のママはうまくやっているのに」──そんなふうに、自分を責めてしまう気持ちに心が押しつぶされそうになることはありませんか?
本記事では、医師監修のもと育児中に陥りやすい“自己嫌悪のループ”の背景や、心を少し楽にするための考え方・対処法についてお伝えします。毎日を必死に頑張るあなたに、少しでも安心していただける時間となれば幸いです。
なぜ育児中に「自己嫌悪」に陥りやすいのか
● ひとりで抱えがちな「理想」と「現実」のギャップ
育児中の親は、「ちゃんとしなきゃ」「子どものために完璧でいたい」という気持ちを強く持ちがちです。特にSNSや育児書などで「理想の子育て像」を目にする機会が多いと、どうしても自分の現状と比べてしまいます。
子どもが言うことを聞かない、自分の感情が抑えられない、家事も育児も思うようにいかない──そうした「思い通りにならない現実」と「こうあるべき」という理想の差が、自責感や無力感を生み、自己嫌悪へとつながります。
● 心身の疲労が“心の余裕”を奪う
育児は24時間休みなしの仕事です。とくに乳幼児期は、夜間の授乳や夜泣き、抱っこの繰り返しで、まとまった睡眠すら取れないこともあります。慢性的な睡眠不足は、脳のストレス耐性を下げ、些細なことでもイライラしたり、落ち込んだりしやすくなります。
本来であれば「少し休めば気分が変わる」ような出来事でも、疲労がたまっていると冷静に受け止められず、「なんでこんなこともできないんだろう」と自分を責めてしまうのです。
● 周囲のサポート不足と「孤育て」の問題
夫婦共働きや核家族化が進んだ現代では、育児を一人で担う「孤育て」状態に陥る方が少なくありません。大人と話す機会が少なく、気持ちを誰にも吐き出せない状況が続くと、心の中に不安や苛立ちが積もっていきます。
「相談する相手がいない」「誰もわかってくれない」と感じる孤独感は、自己否定の感情を深める要因となります。
自己嫌悪のループから抜け出すためのヒント
● 「できていないこと」より「できていること」に目を向ける
自己嫌悪に陥っているとき、人は「できなかったこと」ばかりに意識が向きがちです。しかし、冷静に振り返ってみると、今日も子どもに食事を作った、着替えさせた、一緒に遊んだ──それだけでも十分に頑張っています。
日々の「当たり前」に見える行動の中にも、たくさんの努力と愛情が込められていることに、ぜひ気づいてください。
● 「感情的になってしまう」こと自体を責めない
子どもに強く当たってしまったあと、「なんで怒鳴ったんだろう」と後悔し、自己嫌悪に陥る方は少なくありません。でも、それは“あなたが悪い親だから”ではなく、“疲れた人間”として自然な反応だったのかもしれません。
怒りは悪ではなく、心のSOSサインでもあります。感情が爆発してしまったときは、「今日は本当にしんどかったんだな」と、自分の心の疲れに気づくきっかけと捉えてみてください。
● 頼れる支援は、遠慮なく使っていい
育児はひとりで完璧にこなすものではありません。親族やパートナー、地域の育児支援センター、保健師さん、医療機関など、頼れる支援は積極的に活用しましょう。
「迷惑かけたくない」「こんなことで相談していいのかな」と思うかもしれませんが、あなたの困りごとに耳を傾け、寄り添ってくれる専門家は必ずいます。
医療機関で相談するべきサインとは?
自己嫌悪の感情が続き、「朝起きるのがつらい」「何も楽しいと感じられない」「涙が止まらない」「食欲がない」など、日常生活に支障をきたしている場合は、医療機関に相談することをおすすめします。
とくに、以下のような症状が2週間以上続いている場合は、心の不調が深刻化している可能性があります。
- 気分の落ち込みがずっと続いている
- 寝つきが悪い、途中で何度も目が覚める
- 集中できない、考えがまとまらない
- 子どもや家族と関わることが負担に感じる
これらは、うつ病や適応障害などのサインである可能性もあります。早めの受診によって、心が軽くなるヒントが得られることも少なくありません。
まとめ
育児は喜びに満ちた経験であると同時に、親自身が心身ともにすり減るほど大変な営みです。
自己嫌悪のループに陥っているとき、「こんな自分はダメだ」と思ってしまうかもしれませんが、まずはその疲れに気づき、自分を労わることが回復への第一歩です。
ひとりで抱え込まず、必要なときには医療機関に相談することも、あなたとお子さんの健やかな日々につながります。
このコラムが、あなたの心を少しでも軽くするきっかけとなれば幸いです。
あわせて読みたい
>【医師監修】「育児が辛い」と感じたら?産後うつの兆候と対処法
>【医師監修】ワンオペ育児で夫に嫉妬…産後うつのサインを見逃さないで
>【医師監修】育児ストレスを放置しないで──ママの心のケアも大切です

2025.12.12
【医師監修】育児ストレスを放置しないで──ママの心のケアも大切です
子どもを大切に思う気持ちがあるからこそ、育児に真剣に向き合い、ストレスを感じてしまうことがあります。 「こんなことでつらいと思ってはいけない」と自分を責めてしまう方も少なくありません。 本記事では、育児ストレスが心身に与える影響や、受診を検討すべきサイン、心のケアの方法について、わかりやすく解説...