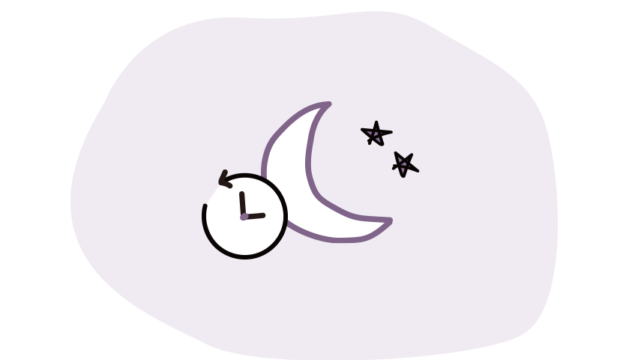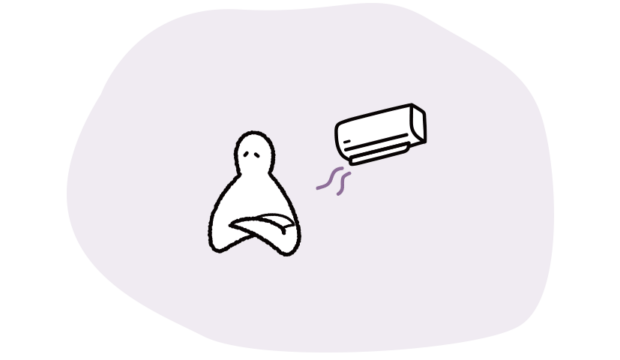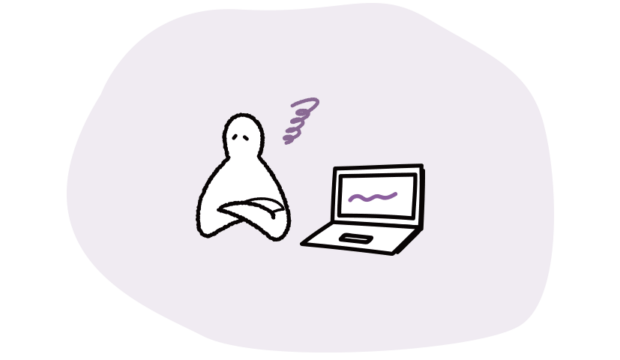夜勤に従事する方は、昼夜逆転の生活リズムや体内時計の乱れから、孤独感や不安感、無気力といった心の不調を感じやすくなります。これらのメンタルサインは、放置すると生活の質を大きく下げてしまうこともあります。
本記事では、夜勤による心の不調の原因や症状、セルフケアの方法、受診の目安などを詳しくご紹介します。夜勤中や日常生活で感じる不調を正しく理解し、必要なサポートを受けるための参考にしていただければ幸いです。
夜勤がもたらすメンタルヘルスへの影響
夜勤は昼夜逆転の生活を強いられるため、体内リズム(サーカディアンリズム)が乱れやすくなります。体内リズムは睡眠・覚醒、ホルモン分泌、体温調節などに深く関わっており、その乱れは心身のバランスを崩す要因となります。
![]()
医療機関で扱うことも多い「夜勤うつ」や「夜勤障害」と呼ばれる状態は、主に次のような症状を含みます。
- 孤独感:夜勤中や帰宅後に家族や友人と会う時間が少なく、心理的に孤立しやすい。
- 不安感:将来の健康や仕事の続行に対する漠然とした不安。
- 無気力:やる気が起きず、日常生活や仕事への集中力が低下。
- 睡眠障害:十分な睡眠が取れず、疲労感が蓄積。
これらの症状が続くと、生活の質が低下し、精神疾患のリスクも高まるため、早期の対策が重要です。
夜勤従事者に起こりやすい精神的症状の特徴
1. 孤独感
夜勤は勤務時間が不規則なため、昼間に家族や友人と過ごす時間が限られます。これにより社会的なつながりが希薄になり、孤独を感じやすくなります。孤独感は、うつ症状を悪化させる要因の一つです。
2. 不安感
夜勤の継続や体調不良、将来への漠然とした不安が増すことがあります。身体の不調や睡眠不足が続くと、精神的な不安が強まりやすくなります。
3. 無気力・やる気の低下
体内リズムの乱れや睡眠不足は、脳の働きにも影響し、集中力や判断力が落ちます。その結果、無気力や意欲の低下を感じやすくなり、仕事や日常生活への意欲が薄れてしまいます。
4. 睡眠障害と疲労感
夜勤では昼間の睡眠が短時間かつ質が低くなりがちです。十分な睡眠が得られないと、疲労が蓄積し、精神的にも肉体的にも不調を招きます。
夜勤によるメンタルサインを見逃さないために
夜勤に従事する方は、自分自身の心の状態を日頃から意識して観察することが大切です。以下のようなサインがあれば注意しましょう。
- いつも以上に孤立感を感じる
- 夜勤後に不安感が強くなる
- 日常生活に意欲が持てない、無気力を感じる
- 睡眠の質が悪く、疲れが取れにくい
- 食欲の変化や体重の増減がある
- 仕事のミスや注意力の低下を自覚する
これらはメンタルヘルス不調の初期のサインであることが多いです。無理をせず、適切なサポートを求めることが重要です。
受診を検討すべきタイミング
夜勤によるストレスや不調が続く場合は、医療機関への相談を検討しましょう。特に以下のような場合は早めの受診がおすすめです。
- 気分が落ち込み、日常生活に支障が出ている
- 不安やイライラが強く、眠れない日が続く
- 無気力感がひどく、仕事や家事が困難
- 自傷行為や自殺念慮がある場合は、緊急の対応が必要
医療機関では、問診や必要に応じて検査を行い、適切な治療やカウンセリングを提供します。早期に対応することで、症状の改善が期待できます。
夜勤従事者のメンタルケア方法
医師が推奨する、夜勤従事者が取り組みやすいメンタルケアのポイントをご紹介します。
1. 生活リズムの工夫
- できるだけ規則正しい睡眠時間を確保する
- 昼間の睡眠環境を整える(遮光カーテンや耳栓の活用)
- 休憩時間に軽いストレッチやリラックスを心がける
2. 栄養バランスの良い食事
疲労回復には、ビタミンB群やたんぱく質をしっかり摂ることが大切です。過度のカフェイン摂取は避け、胃腸に負担をかけない食事を心がけましょう。
3. ストレスの軽減法
- 趣味や好きなことに時間を使う
- 仕事以外の人との交流を意識的に増やす
- 必要に応じて医療機関やカウンセラーに相談する
4. 適度な運動
運動はストレスホルモンを減らし、気分を安定させる効果があります。夜勤前後の無理のない範囲でウォーキングやストレッチを取り入れましょう。
職場での支援の重要性
夜勤は個人の問題だけでなく、職場全体での対応が求められます。勤務時間の調整や休憩の確保、メンタルヘルス研修の実施など、働きやすい環境づくりが必要です。もし職場での相談窓口や産業医がある場合は、積極的に利用しましょう。
まとめ
夜勤に伴う孤独感や不安感、無気力といったメンタルサインは、体内リズムの乱れや生活環境の影響によって起こりやすいものです。医師による本記事の解説を参考に、ご自身の心身の状態を日頃から観察し、早めの対応を心がけてください。慢性的な不調が続く場合は、一人で抱え込まずに医療機関を受診し、適切な治療や支援を受けることが大切です。また、生活リズムの工夫や栄養・運動、職場のサポートもメンタルケアには欠かせません。夜勤を続ける皆さまが少しでも快適に、健康に働けることを願っています。
あわせて読みたい
>【医師監修】「眠れない」「気分が沈む」は夜勤の影響かも?夜勤と心の健康の関係
>【医師監修】介護職に多い“夜勤うつ”とは?セルフチェックと対処法
>【医師監修】警備職に多い“夜勤うつ”とは?セルフチェックと対処法

2025.10.03
【医師監修】「眠れない」「気分が沈む」は夜勤の影響かも?夜勤と心の健康の関係
夜勤を続けているなかで、「寝つきが悪い」「夜に寝ても疲れが取れない」「最近、気分が沈みがち」と感じている方はいませんか? 医療・介護・警備・運送業など、夜勤を含む勤務に従事する方は、日中とは異なる環境のなかで働き続けています。特に夜勤は、体内リズムの乱れや睡眠の質の低下を引き起こしやすく、心の健康...